最近のゲームにおいて、普及と技術進歩の速度はすさまじいですよね。
本よりも小さくて薄い端末で高水準のゲームができる、しかも無料!! なんて小学生時の私が聞いても、信じなかったかもしれません。しかも特定の分野や創造力を教育するために、ゲームを使われることも検討されつつあります。もはや今のゲームは「娯楽」という枠から飛び出しているように思えます。
しかし、だからこそ生まれた弊害もあります。
単純な「娯楽」ではなくなったからこそ、ゲームを楽しむにあたってノイズとなる考え方が生まれつつあるのも事実です。今回はそんなノイズとなる考え方を紹介していきます。
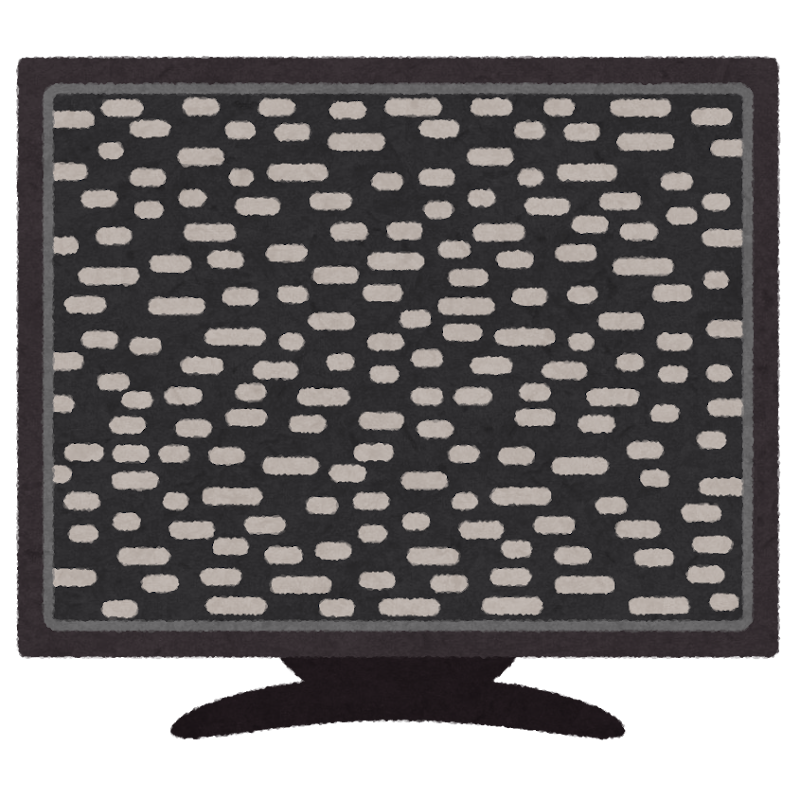
どちらかというと「たまには初心に帰れよ」と自分自身に言い聞かせるために書いています。
まぁ軽い気持ちで読んでみてください。
高グラフィック・オープンワールドであるほどいいゲーム
昨今では既存の大型タイトルや新しいタイトル然り、高グラフィック、オープンワールドを求める声が大きいです。
しかし、私としてはその声に対して思うことがあります。
グラフィックを得て、失ったものは何?
確かに高いグラフィックは、そのゲームが見せる世界への没入感を高めてくれます。
しかし、ある要素がなくてはその没入感はすぐに限界を迎えてしまいます。
それは「できることの多さ」です。
例えばストーリー以外のサブイベントもしくはミニゲーム、着せ替え機能、あとは行けるフィールドの範囲が広い・・・など。できることの多いゲームというのは、飽きにくく長く遊ぶことができます。
しかし、ゲーム開発のリソースは有限です。
世間的に神ゲーと呼ばれるゲームでも、リソースを回せなかった(言い方が悪いですが、手を抜いた)部分は必ずあります。
そしてグラフィックというのは、視覚に働きかけるものであって、磨き上げたからと言ってできることが多くなるわけではありません。
つまり、グラフィックにたくさんのリソースを費やしてしまうと、どこかのリソースを減らさなければなりません。それが「できることの多さ」が減ってしまうことに直結するのです。
グラフィックはいいが、できることが少なく退屈・・・それって果たしてゲームでしょうか?
どちらかというと映画に近いのではないでしょうか?
グラフィックは売り上げには結びつきますが、決してゲームの根幹にはならないと考えています。
ブレワイの栄光と功罪
2017年発売の「ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド」
私もプレイしましたが、非常に満足度の高いゲームでした。
しかしあのゲームの唯一の欠点として、
プレイヤーのオープンワールドに対する認識がゆがませてしまったことが挙げられます。
元々ゼルダの伝説はオープンワールドではありませんでしたが、この作品の根幹の一つとしてハイラルという広大なフィールドの探索がありました。作りこみの高さもそうですが、ブレワイがヒットしたのは、シリーズを通して貫いてきたものが、オープンワールドと相性が良かったからこそ、とも考えています。
でもこの世にはいろいろなジャンルのゲームがありますよね?
アクション、レース、パズル、シューティング、ミニゲーム集・・・など
それらすべてのゲームがオープンワールドと相性がいい、オープンワールドになるべきかといわれると、そうではないですよね。
ここまで長々と話してきましたが、結局何が言いたかったのかというと、
高グラフィック・オープンワールドにする「意味」と「意義」を見出さなければ、逆にゲームの品質を落としかねないということです。
ストーリー攻略だけなんて、もったいない
みなさんはどれくらいのプレイヤーがストーリーをクリアしているかというのは知っていますか?
・・・・30%未満らしいですよ。これを最初に知った時の私の感想を話します。
「いや少なっっっ( ゚Д゚)!!!」
これは実際にゲーム開発に携わっている方が、トロフィー機能によりデータを集計した結果ですので、そこまで大きく外れた結果ではないでしょう。
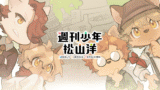
つまり世間的には、ゲームは基本クリアしないのが当たり前ということです。
しかし、ゲーマーの間では全クリ、すなわちそのゲームから課されるすべての課題を制覇しないともったいない、極端な話、そのゲームを語る資格がないと考える人もいます。
その考え方について私が一つ申したいのは、
そもそもゲームは、クリアされる前提で作られたものではない、ということです。
昔のゲームはクリア後という概念はなく、ストーリーをクリアしたら最初から、もしくは終盤手前から始まるのがほとんどです。また、ゲーム中でも絶対に気づけないであろうイベントあアイテムが隠されているということもあります。今でこそ攻略動画や攻略サイトがありますが、昔は自力で発見しなければなりませんでした。
だから全クリをしていない自分を恥じる必要はないと思います。
新しく発見したものがあったなら「やった!!!まだこのゲームで楽しめる!!!」と思えばいいだけです。
思ったより長くなってしまったので、続きは後半に書きたいと思います。
↓ゲーム紹介シリーズ
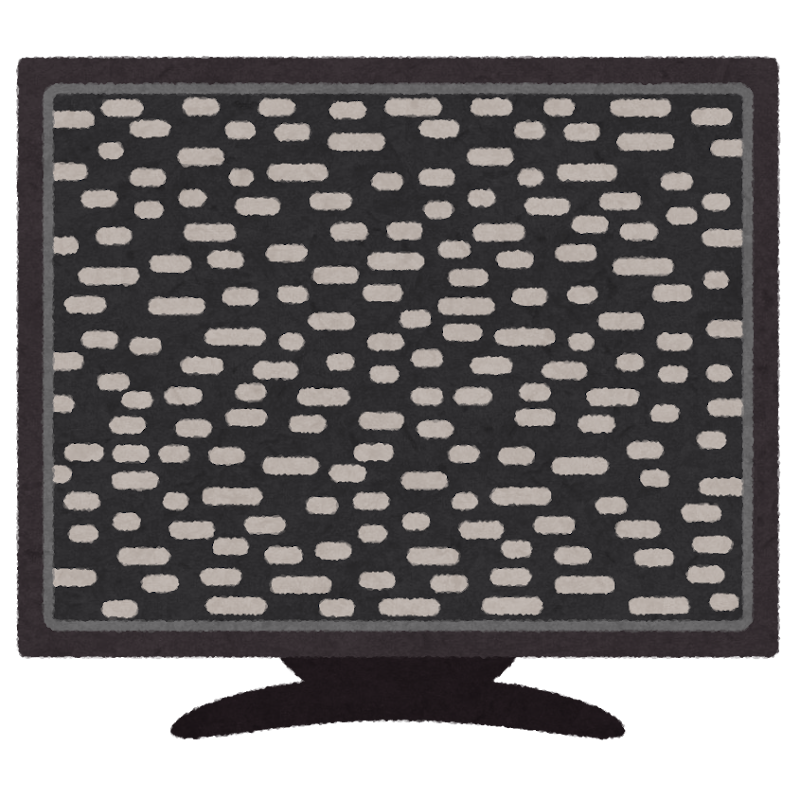
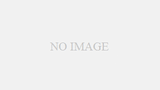


コメント